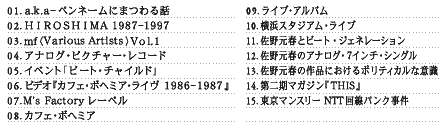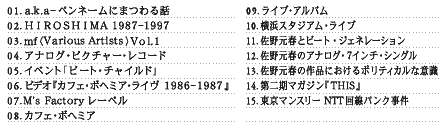佐野元春の作品は、あえて今さら言うまでもなく、広義の意味でのメッセージ・ソングである。さらに付け加えるなら、個人的な想いを伝えるためにポップなフィーリングを盛り込んだダンス音楽だとも言えるだろう。
『VISITORS』『Cafe Bohemia』『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』という1980年代後半の3作のアルバムに貫かれているアティチュードは、ジャーナリスティックな視線を有するダンス・ミュージックであり、クリティカルな視点を持ったソウル・ミュージックであり、ポリティカルな意識を携えたロックンロールである。
社会の中で人間がひとつの意識を持って行動していくとき、決して無視するわけにはいかないのが「宗教」と「政治」である。ダライ・ラマがそうであるように、ひとつの歌(祈り)を継続していくとき、宗教的な発想と政治的な発想が深く関与してくる。ビート・ジェネレーションの詩人や作家が試みた作業というのは、宗教的な意識と政治的な意識に目覚めながら、あくまでも“個”を見つめていくことだったのではないか。そういった意味では佐野の作品はいつも、「月と専制君主」にしても、「99ブルース」にしても、「インディヴィジュアリスト」にしても、決して怒りの雄叫びではなく、祈りの歌なのだ。
佐野元春は『VISITORS』と『Cafe Bohemia』において“ビートは続いていく”というテーマを掲げ、“仲間たちと歩いてゆく”こと、それが最も大切なんだ、と告げた。つまり、この世界の危機的な状況や悪循環に怒りをぶつけるのではなく、混沌とした現実の中を陽気に笑顔で歩いていくこと。そうやって世界と対峙していこう、という態度がここにはある。
その精神性こそが50年代にジャック・ケルアックが、アレン・ギンズバーグが、ゲイリー・スナイダーらビートのオリジネイターたちが試みていたものではないかと僕は思っている。